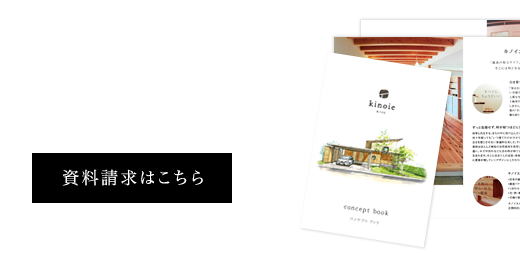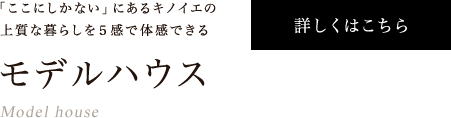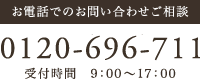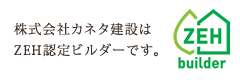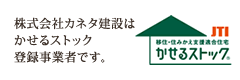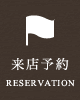木の家マルシェ間もなく開催!~出店者の思い(後編)
September 17, 2016

昨日に続き、いよいよ明日9/18(日)開催予定の「木の家マルシェ」の出店者様の思いをご紹介させていただきます。

地元上越の無農薬米を生産・販売する「農業組合法人ファーム富岡」さん。仲間でチームをつくり、地元で育ったお米を生産者がそのまま地元の食卓へお届けしている頑固一徹な商売を貫いています。野生のサギ達もエサを求めて集まってくるという自慢の田んぼでは、化学肥料や農薬をできる限り使用しない安心安全なお米づくりにこだわり、一粒一粒大切に育て、今年で10周年を迎えています。「地元を大切にし、地産地消でがんばる人には共感する。心から応援したい。」と今回の出店を決めていただきました。

最後にご紹介するのは、「土の香工房cotocoto」さん。cotocotoさんでは、「発酵のまち上越」・「上越の自然豊かで四季折々の美味しい素材」を地域の皆さまをはじめ全国に発信しようと、食材をドライ商品や塩糀の商品作りに取り組んでいます。こちらのcotocotoさんも安心安全はもとより、地域に根差した商品づくりへのこだわりが強く、地元上越地域での住まいづくりを考えるキノイエとはとても馬が合うようです。

木の家マルシェは、いよいよ明日9/18(日)10:00~キノイエ上越モデルハウス「塩屋新田の家」で開催です。ご近所に遊びに行くような気軽な気持ちでぜひお越しください。
また、今後の開催も検討しておりますので、趣旨にご賛同いただける出店仲間も募集しております。詳しくは、0120-470-456 又は info@kaneta.co.jp カネタ建設「木の家マルシェ」担当藤田までご連絡ください。
玄関ホールを使い倒す
September 13, 2016

住まいの設計で、多くの人が壁に当たるのが、「膨らんだ間取りをいかに縮めるか?」という問題。予算とのにらめっこでいちばん神経をすり減らす部分です。夢をたくさん詰め込めば詰め込むほど、それに比例して間取りは大きくなるものです。
そこで、キノイエでは、最初から間取りの足し算ではなく、「引き算する設計」を軸にしたプランニングを行っています。引き算する設計には、様々な極意があります。その一つは、「使わないスペースを極力排除する」、あるいは、「使う頻度の少ないスペースを極力縮める」です。そしてもう一つの方法、それは、「あまり使わないスペースを多機能化して使い倒す」です。

平牛の家 玄関ホール
その分かりやすい一例が玄関ホール。玄関ホールが使われるのは、自分たちの出入りと来客対応時。つまり、使うタイミングは非常に限られており、実際は閉じられたままで使われない時間の方が圧倒的に多いのです。見栄を張らない限り、本来のスペースとしては最小でいいということになります。小さくつくって大きく暮らす設計では、ここを小さくすることが原理原則になっています。

平牛の家 玄関ホールから外へのアクセス
しかし、キノイエでは、あえてこの玄関ホールを普通よりも広く取るケースがあります。まさに、「どうせあまり使わないスペースなら多機能化して使い倒す」の発想です。写真のように、塩屋新田の家、平牛の家どちらも玄関ホールはあえて広く土間スペースを確保し、リビングの中に取り込んでいます。リビング自体の設計面積は、わずか11~15帖程度とかなりコンパクトなのに、この玄関ホールを取り込むことで、こんなにも広々した空間に変わります。そして、この土間空間こそが、外のデッキスペースや庭、離れスペースなどに接続するハブのような存在となっており、一日の流れの中で幾度となく使われる、まるで第二の勝手口のような機能を果たしてくれます。

平牛の家 リビングから玄関ホール(障子で玄関ドアホールを隠した状態)

塩屋新田の家 玄関ホール(引き戸により、土間部分を2つの空間に仕切ることが可能)
「でも、来客があった時は丸見えじゃないの?」という疑問の声が聞こえてきそうですが、ご心配なく。たった一枚の引き戸を入れておくだけで、その時だけ空間を一度遮断し、小さな玄関ホールをつくります。そうすることで、急な来客や宅配便の受け取りなども、プライバシーを確保しながら応対が可能になるのです。
使う頻度が少なければ、発想を変えてよく使うスペースに取り込む。ちょっとしたことが大きな意味を持つ、引き算する設計のちょっとした極意。その一部のご紹介でした。
|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
いちばん伝えたいのは
September 11, 2016

先日、キノイエの「コンセプト会議」(勝手に命名)を行いました。内容はイベント企画や発信方法についてなど様々。

コンセプト会議とかっこいい名前を付けておきながら、実は、関係者数名でコーヒーを飲みながらフリートーク(笑)この日の大きなテーマは、キノイエの良さを伝えるために、いちばん大切なことは何か?でした。
結果、たくさんの素晴らしい意見、アイディアが飛び出しました。でも、落ち着くところ、いちばん大切なことは、「この家の何とも言えない心地よさをとにかく感じてもらうことだよね」という話に(笑)
いいものに理屈はいらない。感情を揺さぶる「何か」がある。その一点にフォーカスした伝え方を整理してみようという話になりました。仕事ながら、こういう時間が楽しいと思える環境に感謝です。
|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
庭づくりの重要性
September 8, 2016

ずっと未完成状態が続いていた塩屋新田の家の庭が、このほどようやく完成しました。

ここまで完了が長引いたのは、竣工当時まだ計画中であった南側に隣接した建物の位置関係、外観の確定を確認した上で、リビングからの視界と、お隣さんからの視線との関係を見極めてからという事情がありました。庭づくりの成否は、隣接する家々との関係を考えてこそ成り立つものです。ソトを上手に取り込み、ナカの暮らしに広がりを生み出す庭の存在は非常に重要。だから、なるべく隣接建物の計画がある場合は、慌てずその完成を待ってから行うのがベターです。
今回の庭づくりにおいては、幸い、こちらのリビング側に面したお隣のお住まいの窓が水回りのすりガラス窓や収納室の窓が中心らしく、普段の生活シーンでほぼ直接的に目線が合うということがないということが分かりました。加えて、外壁もシンプルな黒単色の波型金属サイディングであったために、色彩的な干渉も少なく、周辺の視界を遮る役割も担ってくれています。結果としてプライバシー性の高い中庭のような空間になりました。母屋だけでなく、カーポートや離れとの連続性が生きるこの庭の利用価値はまさに無限大です。なお、西側の敷地はキノイエの住宅建設予定地でもあるため、塩屋新田の家とのつながりも考えて自由に考えることができ、2軒のつながりも含めてこれからのプランニングが非常に楽しみです。

完成といっても、本当の庭づくりは実はこれからが本番。庭に植えられた多くの植物たちがきちんと成長するように面倒を見ながら、小さな森をつくることが目標です。今回、庭木には、モミジやセイヨウカマツカ等の落葉樹に加え、ナンジャモンジャ等、四季折々の表情を楽しめる樹種を選びました。そして、ちょっとした遊び心で、中央に流木を配置。ちなみに、この流木、私たちの住む上越地域では、海岸に行けばそれなりに簡単に手に入る何の変哲もない代物ですが、所変わるとその価値は一気に変わります。特にこの上越地域から内陸部に位置する長野県内に住む方にとって、流木は非常に入手困難な高級品。おそらく、写真のサイズの流木だと、所変われば‟ん万円(?)”になる可能性もあります。

地元に眠る、こうした付加価値の高い素材に目を向け、暮らしの一部に反映させる・・・地元で生まれ育った私たちが家づくりで行うべき、とても大切な仕事であると考えています。家づくりを通して、ご家族にとっての「最高の地元ライフ」を実現すること。それが私たちの仕事です。
|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
「テロワール」と地元の木
August 31, 2016

ワインの価値は、「テロワール」で決まると言われています。
テロワール(Terroir)とは、「土地」を意味するフランス語terreから派生した言葉で、 もともとはワイン、コーヒー、茶などの品種における、生育地の地理、地勢、気候による特徴をさすフランス語です。 同じ地域の農地は土壌、気候、地形、農業技術が共通するため、作物にその土地特有の性格を与えると言われています。その独特の地域性がワインの個性となり、その違いがそれぞれのブランドにつながっています。つまり、地域性がブランド競争の原点になるというのがワインの世界の常識です。
さて、本日は、ワインとは関係ありませんが、このテロワールに関連するようなお話を家づくりに絡めてしてみたいと思います。

私たちは、定期的に地元の製材屋さんと情報交換をしています。
新鮮な情報は現場にあります。お客様のために、少しでもよい材料の選別や、最新の加工技術の情報交換もさることながら、時には、昨今の木材市況の話や経営の話に至るまで、内容は多岐に渡ります。

その中で、最近特に頻繁に話題に上がるのは、「地元産の木材がなかなか思うように出荷できない」というもの。その深刻さは年々増しているようです。最大の要因は、住宅そのものが工業規格化されていき、かつ室内はビニルクロスで覆われ、構造材としてはほとんど見えない家づくりが主流になってしまったため。海外の安価な材料が市場に出回り、国内各地で製材をしても品質の良さが伝わらず、価格競争で埋もれてしまうという話は、全国の製材業に共通する悩みでもあります。

そのような市場背景のため、国内では数十年前に国策で植林された非常に質の良い、主に杉材を中心とした原木が、伐採されることなく眠っているケースも少なくありません。

仮に、運よく切り出された原木でも、主たる構造材や造作材として製材されずに残ってしまっているものが多く、出荷されずに年数が経ってしまうと、今度は劣化が始まり、黒ずんだり、肉痩せや変形を生じ、最後は製品としての価値を失ってしまいます。また、そのような環境が伐採業者の衰退を生み、今では、街中の老木に倒壊の危険性が発生しても伐採処分ができる職人をすぐに手配できないという状況も生まれています。
地元の気候風土の中で育ち、いちばん身近にある天然の材料なのに、使われないままでいるのは、非常に勿体ないことです。

そこで、私たちのような家づくりの立場と、木の特性をいちばんよく知る製材工場の立場のスタッフが膝を突き合わせ、「地元の木の生きる道」について真剣に語り合うことがとても重要な意味を持ちます。お客様のニーズ、その木のもつ特性、価格、利用価値・・・これらについて自由に意見をぶつけ合っていると、ふとした時に、素晴らしいアイディアが生まれる場合があります。

キノイエの標準仕様である杉板の外壁材(以前のブログでも紹介)は、そうした製材工場の中で、品質は上等ながらも運悪く眠っていた地元糸魚川産の杉材を、キノイエのデザインのためだけにオリジナルピッチでカットして生まれたものです。価格も手ごろで、輸入材にはない独特の風合い、そして何より「地元で生まれ育った」ストーリー(=テロワール)の重みが、住まう人にとって特別な意味と愛着につながります。

他にも、以前のブログでご紹介した、地元杉の幅はぎ材でつくられたオリジナルテーブル。デザイナー家具の良いところを応用しつつ、材料は地元調達。製材屋さんとじっくり吟味し、価格と品質のバランスのいいものだけを厳選し、いちばん杉の木目が美しくなるように合わせていくことで、価格以上の付加価値を持たせることができます。

地元の木を地元の職人が切り出し、地元の技術者が加工し、地元の住まいに利用され、地元の人々の暮らしと共に愛され受け継がれていく。――この美しい地域循環に魅力を感じる人は、けして少なくないと思います。家づくりにテロワールの考え方を持つことで、もっと自分たちの住まいに愛着が深まるのではないでしょうか?
まさに「最高の地元ライフ」。――私たちは、そうしたことに共感していただける皆様に、手間暇を惜しまず、しかし手の届く最高の暮らしをお届けしたいと考えています。
|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
床と天井の連続性
August 29, 2016

床から数十センチ浮いたテレビボード。

天井から壁がつながっていない和室。

手前に見えるパントリーもよく見ると、天井から少し空間が空いています。

二階の天井も同様に、水回りスペースの上は小屋裏収納がむき出しに・・・

お気づきですか?床と天井の連続性は、空間の広がりに直結します。
小さくつくって大きく暮らす。コンパクトでハイクオリティ、かつコストバランスのいい住まい。引き算の設計とは、単に間取りを小さくするだけではない、様々な工夫がちりばめられているのです。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
夏の終わり
August 28, 2016

もうすぐ夏休みも終わります。
皆様はこの夏、ご家族とどのような思い出をつくりましたか?私たちの暮らす上越地域は、海、山、川に囲まれ、望めばいつでも自然の恩恵に触れることができます。まさに、最高の地元ライフ。
こちらは、キノイエスタッフのある夏休みの一日です。


糸魚川市能生地区にある弁天岩。糸魚川の周辺の海岸は砂利浜が多くなりましたが、こちらの海岸は遠浅で砂浜もたくさんあるので、毎年家族連れでにぎわいます。

大胆なサービスショット!さて、どのスタッフの家族でしょう?

正解は代表猪又の家族。こちらは三女、まおちゃんでした(笑)
|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
美しい現場(10S+A・T)
August 26, 2016

弊社では、毎月定期的に建設現場のパトロールを行っています。


パトロールのチェック項目は非常に細かく設定されており、安全衛生はもちろん、品質、そして現場マナーのあり方に至るまで、厳しいチェックが入ります。チェックの入った項目は、すぐに改善指摘事項として担当者並びに関係する全ての協力業者に伝達される他、それ以外の全ての協力業者の皆様にパトロール実施報告書として配布されます。
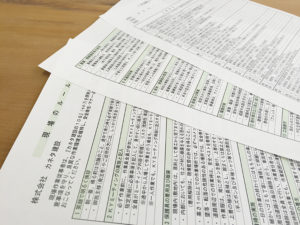
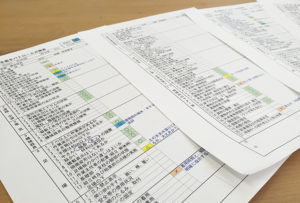
ちなみに、パトロールには、安全衛生担当者の他、現場担当以外の営業スタッフや建築スタッフなども参加します。さらに、弊社のスタッフの他にも協力企業のスタッフさんにも持ち回りで参加していただき、一つひとつの現場について社内外の厳しい目でチェックしていきます。担当者以外のメンバー複数の目で見ることによって、担当者にとっての都合のいい現場品質ではなく、誰の目から見ても納得のいく「美しい現場づくり」のための様々な是正要求や改善アイディアが集まってきます。また、参加した協力業者の担当者にも当事者意識が芽生えてきます。まさに、”終わりなきカイゼン”のための「善の循環」のような仕組みを目指しています。

ところで、「美しい現場」とはどういう現場なのか? 私たちは、こんな指針をつくりました。

写真は、「10S+A・T」と呼ばれる、建築現場に入る者が徹底するべき事項をまとめた弊社独自の指針です。「5S、(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」という言葉を聞いたことがある方は非常に多いと思いますが、私たちはさらに項目を増やして10Sとし、そこに「挨拶(A)」と「体調(T)」の2項目を加えて、自社のスタッフ、協力業者の皆さんに周知徹底を図っています。
10S+A・T
【1A 挨拶】
朝一番、帰る前、仲間や周辺住民への挨拶は明るく笑顔で
【1S 整理】
いる物といらない物を分けて、いらない物を捨てる
【2S 整頓】
いる物を所定の場所に、使いやすいように置く
【3S 清掃】
身の回りや職場を、常にゴミや汚れの無い状態にする
【4S 清潔】
整理、整頓、清掃の3Sを維持し、きれいに保つ
【5S 躾】
決められたルール・手順を正しく守る
【6S 作法】
礼儀作法を身につけ、態度・言葉使いに配慮する
【7S 参加】
安全な現場環境作りは、全員参加が原則
【8S 習慣化】
作業方法や行動が身に付くまで徹底する
【9S 設備】
機械設備や作業用設備を安全に維持する
【10S 即実行】
気付いた事や、やるべき事は後回しにしない
【1T 体調】
元気な体と精神を維持することは全ての基本
いい仕事をする人は、現場も道具もきれいだと言われています。こうした活動を地道に続けることで、まずは「人」を磨き、本当の意味で「美しい現場」、そして「よいチーム」をつくっていきたいと思います。
|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
高さを節約すると
August 23, 2016

塩屋新田の家の二階天井は、屋根勾配に沿って地元糸魚川産の杉板がふんだんに貼られています。

その杉板の天井は、水回りスペースの上に空いたわずかな隙間の先にまで伸びています。これは、視覚的な広がりをつくる、小さな邸宅設計の基本的な技でもあります。
そして、その隙間部分は、そのまま小屋裏空間として、大容量の収納スペースになっています。

キノイエは、小さくつくって大きく暮らす――引き算の設計が基本です。この小屋裏収納の確保にあたっては、面積的な引き算だけでなく、合理的な階高の引き算をした結果生まれた”おつり”を有効利用してつくられました。だから、このスペースをつくるために構造的な足し算は一切ありません。コストを上げずに収納をプラスしました。ほんのわずかな階高の節約(といっても、この方が視覚的にも省エネの観点からも理に適っています)も逃さない設計が、想像以上の使い勝手を実現させています。

|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|
行き止まりをつくらない設計
August 22, 2016

小さくつくって大きく暮らす――引き算する設計で最も必要なことは、ムダな動線をつくらないことです。

そのためには、住まいの中に極力行き止まりをつくらないことです。例えば、塩屋新田の家では、いちばん長く過ごす場所でもあるリビングダイニングの空間に、以前のブログでもご紹介した小さなパントリー(キノイエオリジナル「箱パントリー」)を中心に周りを回遊できるように設計されています。

小さな空間にキッチンとパントリーを設置すれば、少しでも収納を確保したくなるため、大抵キッチンの奥は行き止まりになるのが普通の設計です。しかし、そこにほんのわずかでも人が通れる空間を設けることで、リビングダイニングとの連続性が生まれ、想像以上の自由度と開放感が生まれます。

開放感は面積ではありません。行き止まりのない、自由度がある動線をつくることにヒントがあるのです。
|上越・妙高・糸魚川で最高の地元ライフ|自然素材の注文住宅|木の家をつくる工務店|小さな邸宅|キノイエ|www.kinoie-niigata.com|0120-470-456|

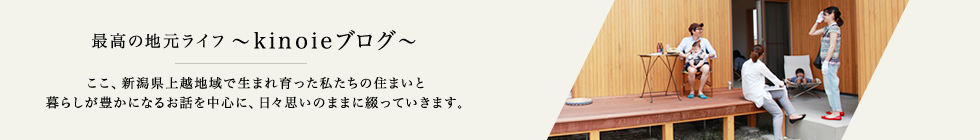

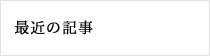 最新の記事
最新の記事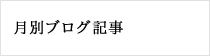 月別ブログ記事
月別ブログ記事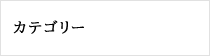 カテゴリー
カテゴリー